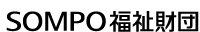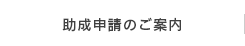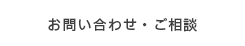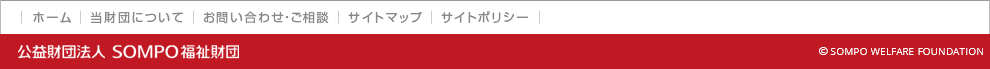第21回損保ジャパン日本興亜福祉財団賞 文献要旨
『住宅扶助と最低生活保障−住宅保障法理の展開とドイツ・ハルツ改革』
佛教大学社会福祉学部 教授・嶋田 佳広氏
1 本書の目的
比較法研究は、我が国の法学研究において一大分野をなすものである。後進国スタイルなどと常に揶揄されながらも、21世紀に至ってもなおもしっかりとその命脈を保っている。日本のあり方を相対化する点で重要な役割があるからであろう。とりわけドイツ法研究は、明治以来の伝統を誇り、もはややり尽くされた感すらあるが、しかして仔細に見れば、実はそうでもない。判例研究という意味での法学は確かに後追い的にならざるを得ないとしても、その遅れるワンテンポを可能な限り縮めていき、判例から垣間見える社会の実相をあたう限り再現・発見していくことで、我が国と比較対象国とを一定程度パラレルに評価する可能性がまだまだあるのである。言い換えれば、すでにドイツで確立した何かを後から日本語にして出羽守をするだけではない、ドイツでもよく分かっていないテーマにあえて焦点を当て、日本の発想では思いも付かない何かを探し当てること、それこそが本書における研究方法を貫くバックボーンである。
ドイツの社会保障といえば、伝統的には社会保険を中心に語られてきた。日本における紹介もそうであるし、当のドイツ自体も、教科書は社会保険中心に記述されている。しかし、社会保険でない社会保障も存在する(社会保障という概念自体が英米のプラグマティズム由来であるため、ミスリードではあるがここでは深く立ち入らない)。主として租税を財源とする社会保障制度はドイツでもそれなりに発達しており(例えば住宅手当)、分けてもいわゆる公的扶助に分類される制度は独特の発展を示してきた。そのこと自体の紹介は日本でもそれなりに存在するところであるが、いったい日本と何が違うのか、どう違うのか、なぜ違うのか、本格的な法学研究の蓄積が−例えば他の法学分野:公法や私法、刑事法、労働法などと比べて−十分にあるわけではない。
そこで本書は、公的扶助を実際に構成するドイツの制度に着目し、とりわけ給付のあり方、組み立て方、基本的な考え方をひもといて、ドイツの特徴を明らかにすることとした。その素材として、住居費給付(日本でいう住宅扶助)における判例法理の成立・展開を跡づけ、具体的な問題の所在と、大きな説明概念である構造原理との関係を考察し、ドイツの現時点での着地点を確認しようとしたものである。
2 本書の概要
構成に従って概観する(序章は省略)。
第1章は、比較法研究の前提として、我が国の現状理解を試みた。一つは、生活保護の総論との関係で、我が国の生活保護行政における過度のマニュアル重視の弊害の現れとして、個別事例への着目が弱く、必要即応原則の機能する余地がほとんどないことを確認した。もう一つとして、各論的視点から、扶助の一種である住宅扶助について、その基本的性格に言及した。住宅扶助は名目的には実費支給をうたうにもかかわらず、固定的な上限がかせられており、実質的な打ち切り支給の体をなしていること、それゆえ他の扶助への住居費需要の食い込みが生じていることを指摘し、食費などと違って可変的でない住居費需要において一律上限を設けることの合理的を問うた。
翻って第2章では、まずドイツの公的扶助法制全体の動向に着目した。かつては日本と同様一つの法律(連邦社会扶助法)が公的扶助を形成していたところ、折からの労働市場改革(ハルツ改革)に巻き込まれ、稼得能力の有無で制度自体を切り分ける改革が大胆に導入された。この改革は、伝統的な社会扶助に多くの変容を加えるものとなり、とりわけ、基準額給付(日本でいう生活扶助)の性格を著しく一律的・包括的にさせてしまった。改革前であれば基準額給付が対応すべき需要は限定され、不規則な需要や未知の需要には別枠の給付で対応していたが、これが基準額給付に押し込まれ、受給者の側で給付管理をするシステムに移行したのである。しかしこのような改革後の基準額給付は憲法違反であるとの司法判断が最終的に惹起された。この点はドイツ公的扶助の原理的理解に関する問題であるが、いずれにしてもドイツでは、見捨てられる需要はないはずだ、という基本的立場が維持されることになったのである。
こうした総論的展開を受け、第3章では、住居費給付の制度構造と法的紛争を追及した。ドイツの場合、住居費給付は、適切な実費を支給する、というシステムになっている。つまり(少なくとも名目上は)固定の上限を要扶助者にあてはめるのではなく、むしろ一件一件(一軒一軒)の家賃額についてそれぞれ適切性を判断するのである。もちろんドイツにおいても、無条件で家賃全額が公的扶助による保障対象になるわけではない。それどころか、現象面では日本と同様、実施機関が高額すぎるとみた家賃は一部がカットされて給付される。日本との違いは、この住居費一部カットが裁判所で徹底的に争われる点にある。そして裁判所もまともに審査し、住居費カットの合理性、適法性を、実施機関に徹底的に問い詰め、あるいは、個別事情の有無を受給者に徹底的に問い、そして争いは最高裁にまで至るのである。そのなかで、公的扶助の原理原則が個別具体の給付において可視化され、判例法理が形成されてきた。そうした展開の一方で、上述のハルツ改革および基準額給付違憲判決の影響を受け、住居費給付にも新たな様相が生じてきた。それまで内部基準に過ぎなかった各実施機関における住居費の適切性判断基準について、連邦州ごとにルールを設けようというのである。この動きは全面化には至ってはいないものの、ドイツの伝統的なあり方(原理)を大きく変える可能性を秘めている。
第4章では、一種の思考訓練として、以上のようなドイツの問題状況を総論的に議論することを試みた。ドイツ公的扶助を貫く需要充足原理という重要な原理的思考体系を手がかりに、一時給付や住居費給付、基準額給付といった具体に給付のあり方が原理的思考からどのように捉えられ、規定されるのか、そしてその意味は何かを考究した。また、法律の作りとの関係で司法審査を引き込みやすいドイツの特徴を念頭に、公的扶助の保障モデル、換言すれば最低生活保障の方法論について検討した。
終章は、社会保障法の分野であると一般的には考えられてこなかった住宅保障について、公的扶助以外の議論可能性について簡単に触れている。
3 残された課題
ドイツの基本的な発想である、公的扶助に至ったがために現在住んでいる住居を追われるべきではない、という現住住居保護の考え方は、残念ながら日本ではまったく受け入れられていない。豊かな生活保護か貧しい生活保護か、まさに基本的なところが問われている。ただし生活保護だけあればよい、というわけではない。生活保護のレベルより上の、住宅(の保障)にかかる実効的な諸施策があってはじめて、生活保護の守備範囲は定まる。その意味で、住宅政策についての研究をより深め、あるいは災害対策など隣接領域についての知見を蓄え、それらを踏まえて、大きく社会保障の視座から住宅について検討を進めていかなければならない。
4 最後に
本書は、前任校である札幌学院大学から、札幌学院大学選書として刊行された。研究の場と出版助成を与えてくれた札幌学院大学に心から感謝したい。