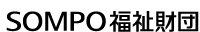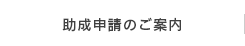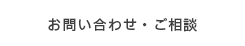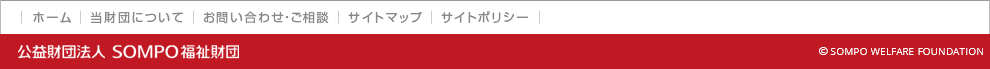第9回損保ジャパン記念財団賞 受賞文献要旨
[著書部門] 『障害とは何か−ディスアビリティの社会理論に向けて−』
東京大学先端科学技術研究センター 特任助教 星加 良司
本書は、「ディスアビリティ」という概念に着目して、社会的現象としての「障害」を理論的に把握するための適切な認識枠組を提示しようとする試みである。
序章では、本書の目的を、他の「問題」との弁別の基準を持ち(「同定可能性要求」)、論理的な水準で解消可能性に開かれ(「解消可能性要求」)、解消要求の規範的・経験的妥当性を主張することができ(「妥当性要求」)、内部の質的な多様性を適切に表現し得る(「多様性要求」)ようなディスアビリティ理論の探求、と位置付けた上で(第1節)、本書の構成を示した(第2節)。
第1章では、1970年代から活発化したディスアビリティ理論の展開を、「個人モデル」から「社会モデル」へのディスアビリティ理解のパラダイムシフトが持った認識論的な意義に着目して整理し、そこでどのような前提が共有されるようになったのかを明らかにした(第1節)。 その上で、そうした前提を共有する現状のディスアビリティ理論では十分に掬い上げられない問題について、高齢者施策と障害者施策との「統合問題」、労働における差別禁止の実態的効果、自己決定の理念が有する両義性や限界、といった論点を取り上げながら指摘し、現状のディスアビリティ理論の限界を照射した(第2節)。
第2章では、従来の「社会モデル」の理論構成においては、障害者の経験する不利益を特有なものとして同定することができず、結果として、その解消の主張の論理的妥当性が減殺されていることを確認した上で(第1節)、ディスアビリティ理解の焦点である不利益について、規範的論点を含む新たな概念化を提示した(第2節)。また、この再定式化を踏まえて、「不利益の更新」という原理的な問題の存在を示し、不利益解消の望ましさをめぐる規範的な問いを明確にした(第3節)。
第3章では、不利益解消をめぐるポリティクスの中で、障害についての従来の議論がいかなる基準に基づいて、いかなるタイプの規範的主張を行っているのかを概観した上で(第1節)、このテーマについての最も深化した理論であると思われる立岩の一連の論考について検討し、その意義と限界について明らかにした(第2節)。そして、そこで得られた知見と着想を引き継いだ上で、その限界点を突破する可能性を持つ新たな視角として、不利益が特有な形式で集中する現象としてディスアビリティ概念を把握することを提案した(第3節)。
第4章では、従来看過されてきたディスアビリティの非制度的位相の存在に着目し、そこでのディスアビリティ生成のメカニズムについて素描した(第1節)。さらに、本書で主張するディスアビリティ概念の組み換えのポイントを改めて整理した上で、現在世界的に最も広範に影響力を有する障害認識の枠組みであるICF(国際生活機能分類)との、理論的異同について確認した(第2節)。
第5章では、ここまでの議論の文脈の中に、障害をめぐる様々な思想や運動を位置付けることによって、本書の提示するディスアビリティ理論の現実的妥当性について検討した。
まず制度的位相においては、従来のディスアビリティ理論によって正当化される範囲を超えて、ディスアビリティ解消の妥当性を主張しうる可能性が開かれることが示され(第1節)、また非制度的位相においては、従来ディスアビリティ解消の文脈で把握されてこなかった実践の中にディスアビリティ解消の可能性を見出しうることが確認された(第2節)。
そして最後に、本書の議論を通じて障害のインペアメントの側面に関する問題に、どのような知見が付け加えられることになったのかを粗描した(第3節)。
終章では、本書の議論によって、「同定可能性要求」、「解消可能性要求」、「妥当性要求」、「多様性要求」の観点において、ディスアビリティ理論にどのような貢献をなし 得たこ
とになるのかを整理した上で(第1節)、残された課題と社会学の役割について確認した
(第2節)。
最後に、このたびの受賞に際し、これまで様々な形でお世話になった先生方や同僚に心より感謝申し上げるとともに、今後いっそう研究に精進していくことをお約束したい。
[論文部門] 小児がんで子どもを亡くした母親の悲嘆過程
―「語り」からみるセルフヘルプ・グループ/サポート・グループへの参加の意味
法政大学現代福祉学部 任期付専任助手 金子 絵里乃
この論文は博士論文の一部であり、多くの方々の支えのなかで生まれました。涙を流し、また、笑顔を浮かべながらご自身の体験をお話して下さいました15人の方の語りがあって初めて姿を現すように思います。
「子どもを失うのは未来を失うこと」という言葉が物語るように、親は子どもを失うことによって幾重にも広がる悲嘆を体験し、それと共に新たな一歩を踏み出していきます。そのきっかけとなる場の1つとして、近年わが国で注目されているのがセルフヘルプ・グループ(Self-Help Group)やサポート・グループ(SupportGroup)です(以下、SHG/SGと省略)。先行研究を検討すると、さまざまな悲嘆を体験した親が、なぜSHG/SGに参加することを決め、参加してどのような体験をするのか、また、親にとってSHG/SGに参加することがどのような意味をもつかについて明らかにされていないことがわかりました。
このような背景から、小児がんで子どもを亡くし、SHG/SGに参加した体験をもつ母親が語ったライフ・ストーリーを素材に、4つの軸(グループに参加する前、参加した背景、参加した時、参加した後)から悲嘆過程を分析し、分析結果から得られた知見をもとに考察を行いました。なお、研究方法はライフ・ストーリー法を用いました。
分析の結果、グループに参加する前については、解放感を抱く、ショックを受ける、身の置き所を失う、現実を受け容れられない、人と疎遠になる、家族関係の変化というカテゴリーが見出され、参加した背景については、黙された悲嘆と参加への踏み出しというカテゴリーが見出され、参加した時については、現実を直視する、固定観念を取り外す、生きる力を見出す、自己の変化を認識する、悲嘆が深まるというカテゴリーが見出され、参加した後については、バランスを保ちながら生活する、子どもとのつながりを維持する、気持ちを立て直すというカテゴリーが見出されました。
以上の結果から、母親の悲嘆過程とは、これまでに言われてきたように悲嘆を乗り越えたり、そこから回復して生きていくことをゴールとするのではなく、精神面や対人関係において落ち込みと安定の状態を往復してバランスを保ちながら、悲嘆と共に子どもと共存して生きていく過程と考えられました。そして、母親にとってSHG/SGに参加することの意味とは、たとえ継続的にグループに参加しなくても、参加したことで仲間と思える人と出会い、その後、仲間と交流を続けることによって、子どもを亡くしてから時間が経過しても、母親が悲嘆と共生し、子どもと共存する居場所と空間を得られることにあるのではないかと思われます。
また本研究では、子どもを亡くした親のSHG/SGがもつ援助的要素として、新たな知見が4つ見出されました。1つは黙された悲嘆が開きだされること、 2つめは母親が母親という役割から自己を解放する機会を得ること、 3つめは母親が悲嘆の渦中から距離を置いて気持ちを整理する機会を得ること、 4つめは知覚の変化であり、母親はグループに参加することにより、環境によって作られた固定観念を取り外すようになっていました。
ところで、子どもを亡くした体験が同じであっても、グループに参加する全ての母親が参加者と気持ちをわかち合い、安心感を得るわけではないことが分析結果で明らかになりました。グループのスタイルが合わなかったり、気持ちが重なり合わずにズレを感じることが多い場合にはわかち合いは難しく、グループが居心地のよい場になるとは限らないことが示唆されました。
最後になりますが、調査にご協力して下さいました15人の方と「財団法人がんの子供を守る会」、法政大学現代福祉学部の教職員の皆さまをはじめ、いつも暖かく見守りご指導して下さっている先生方や大切な仲間、この度ご推薦して下さいました方々に心より感謝申し上げます。