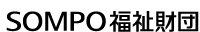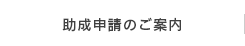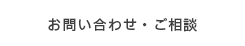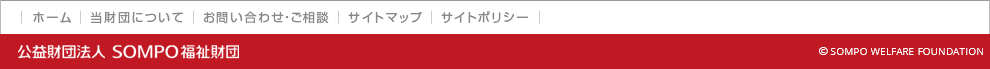第6回損保ジャパン記念財団賞 受賞文献要旨
[著書部門] 『中途失聴者と難聴者の世界』
第一福祉大学人間社会福祉学部(通信教育部)心理学博士 助教授 山口利勝
聴覚障害者は一般的に、ろう者、難聴者、中途失聴者という3つのカテゴリーで表されるが、言語的には、手話を第一言語とするろう者と、日本語を第一言語とする中途失聴者と難聴者に、2分できる。
本書は後者、すなわち中途失聴者と難聴者(以下、中失・難聴者)に焦点をあてたもので、彼らが抱えるコミュニケーションの困難が、健聴者と世界を共有することを難しくしていることを、社会学、心理学、文化人類学、精神医学などの視点から検討した。
第1章では、複雑な聴覚障害者の世界の全体像を示す試みを行った。聴覚障害者のカテゴリーは、聴覚障害を負った時期、聴力、聴能、言語、教育歴、アイデンティティ、及びコミュニケーション手段のどれを重視するかによって捉え方が異なってくるが、この問題をオーディオロジー、言語・文化、定義などの視点から検討した。なお、コミュニケーションの困難は住む世界が違っているという感覚を聴覚障害者にもたらしているが、この感覚をエスノメソドロジーの方法を用いて考察した。
第2章では、コミュニケーション不全が中失・難聴者に及ぼしている問題について論じた(話すことに支障のない中途失聴・難聴者にとっては、聞き取りの困難が問題となる)。中失・難聴者のコミュニケーション不全は、一人でいる時、健聴者と1対1の時、健聴者集団の中にいる時、で様相が異なることを指摘し、それぞれの状況における代表的な問題を検討した。次に、コミュニケーションの問題を、理解やコンテクスト(ルーマンの理論から検討)、及びニュアンスやコンサマトリーなコミュニケーションなどの視点から考察した。
第3章では、中失・難聴者に起こりがちな反応や行動について論じた。具体的には、物事をあいまいなまま受け入れてしまう、状況にマッチした適切な行動がとれない、スティグマに気づかれないように振る舞う(ゴッフマンの理論から検討)などの問題を取り上げて考察した。
第4章では、中失・難聴者が苦しめられている、障害の見えなさについて論じた。聴覚障害者は障害の印が身体の上に見えず、また聴覚障害に関わる様々な要因(聴覚障害を負った時期、聞こえの程度など)も見えないという、わかりにくい存在である。聴覚障害に関わる見えなさによって、中失・難聴者が直面している困難や問題を、障害の説明、コミュニケーション・サポート、主体性などに焦点をあてて考察した。
第5章では、中失・難聴者の精神的危機について、精神医学の視点から論じた。中失・難聴者の精神的苦悩を理解する上で重要な視点が含まれている和田秀樹の論文に注目し、和田と筆者の体験の比較考察を試みた。
主な考察は、和田が自己体験の分析で言及している、中安信夫の状況意味失認モデル、ブランケンブルクの自明性の喪失、ミンコフスキーの現実との生ける接触の喪失(分裂性優位)に関するものである。
考察においては、状況意味失認や自明性の喪失につきまとわれ、現実との生ける接触を喪失している中失・難聴者ほど、アイデンティティの危機に直面し、統合失調症と似たような状態に陥っていることを指摘した。
第6章では、中失・難聴者が、どうすればストレスなくいきいきと生きていけるかについて論じた。不正確で紋切り型の報道が中失・難聴者の理解を妨げている現状を検討し、中失・難聴者の理解が進まない原因を、社会学や文化人類学の視点から考察した。さらに、バリアフリーの問題に言及し、[1]中失・難聴者に対するコミュニケーション・サポートは、手話ではなく要約筆記が重要になること、[2]中失・難聴者には慣れよりも理解が重要になること、[3]中失・難聴者が社会参加する際に、日本的な思考や基準(員数主義など)が心の壁になっていること、を指摘した上で、中失・難聴者に対する最も基本的で重要なバリアフリーの手段は書くことである、と主張した。
[論文部門] 「高齢者福祉施設スタッフのQWL測定尺度の開発」
関西福祉科学大学社会福祉学部 専任講師 李 政元
増加の一途をたどる介護需要、家族の介護機能の脆弱化、そして日本の厳しい住宅事情などを考慮すると、日本の介護福祉施策は当面、高齢者福祉施設(以下、施設とする)を基軸に推し進められるであろう。そこで、施設における介護サービスの充実を検討するならば、単にハードを増やせば良いということではない。利用者本位の視点に立ったソフト面からのアプローチも必要になる。特に、スタッフの質の充実とその確保は急務であり、施設はスタッフの質向上に向けた人的資源管理を展開する必要がある。しかしながら、日本の福祉分野における人的資源管理に関する研究は乏しく、人的資源管理論のコア概念ともいえる職務満足についても、施設職員を対象とした測定尺度の開発は十分とはいえない。
このような状況を受けて、本研究では、福祉施設の人的資源管理に関する研究の1つとして、職務満足よりも包括的な概念、「労働生活の質:Quality of Work(ing) Life」(以下、QWLとする)に注目し、施設で働くスタッフ(看護職員、介護職員、生活指導員)の主観的QWLの測定尺度(以下、QWLSCLとする)を開発することを目的とする。
AlderferのE.R.G.理論に依拠しながら、施設スタッフの職場環境における、〔待遇への満足〕〔上司との関係満足〕〔同僚との関係満足〕〔成長満足〕の4つの基本的欲求に対する満足感を測定する18項目からなるQWLSCLを開発した。QWLSCLの妥当性と信頼性を検証するために、共分散構造分析を用いて、近畿圏某県K市の介護老人福祉施設で働く575名からえたデータに検証的因子分析を施した。分析の過程で冗長な3項目が削除され、本来18項目からなるQWLSCLは15項目に改訂された。二次因子モデルの検証的因子分析によって示された適合度指標(GFI=.984, AGFI=.978, CFI=.978, RMSEA=.058)は何れも、15項目版QWLSCLのデータへの適合の良さを示した。よって、QWLSCLは構成概念妥当性を持つ尺度であることが確認された。また、QWLの因子得点は、〔全体的職務満足〕〔職場継続意向〕〔非職業生活の満足感〕を有意に予測することが確認された。
今回の調査は、近畿地方某県K市に所在する37施設で働くスタッフに対象者を限定しており、QWLSCLの外的妥当性の検証は、今後の課題として残される。また、QWLSCLの開発過程においてQWLの下位次元の設定と質問項目の作成はもっぱら理論演繹的に行ったが、施設スタッフの業務の特殊性を考慮すれば、彼ら固有のQWLの下位領域の存在を否定できるものではない。内容的妥当性の検討も含めて、今後、施設スタッフへのインタビューや自由記述回答による質問紙調査など柔軟な研究方法によって彼らのQWL内容を検討すべきである。
上述のとおり、今回開発を試みたQWLSCLは、幾多の重要な課題を残しつつも、施設スタッフの人的資源管理研究に一滴ながらも重要な知見をもたらすと思われる。特に、新たなQWL測定尺度の開発に際しては、QWLSCLが批判的たたき台となり、QWLが依拠すべき理論、下位次元の設定、そして測定尺度の網羅性を検討できるのではなかろうか。
なお、本研究は、2004年に提出した博士学位請求論文「高齢者社会福祉施設ケアワーカーのQWLとその多様性に関する実証的研究」で重要な位置を占める。本研究では、施設スタッフの平均的なQWLの内容を捉えたが、それを起点とし、QWLの内容は個人・集団によって異なることを生態学的アプローチによって部分的に実証されたことを付記する。